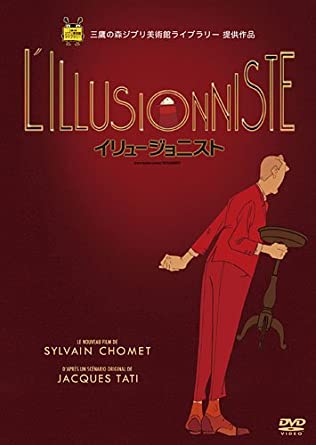とてもよかったけど切ない映画
80分という短い時間の中に、人生の縮図を描いたすばらしい作品だった
絵がとてもやわらかくって優しいから最後まで楽しく観れた
やっぱり絵って大事だと思う
とくにこの作品はアップをあまり使用していない
最近の映画は俳優やキャラクターの顔のドアップを見せつけて無理やり表情を読み取らせようとしている作品が多い
この映画はそれがない
観客は自分で気になる人物の動きを目で追う
そして表情はもちろん、動作や動きなど細かい部分から全体を見て、それで判断する
まずこの作り方から注目したい
こうすることで一種の劇場で演劇を観ているような感じもする
なにより、その場にいて自分(観客)が観察しているような錯覚を起こさせる
これがとても大事な部分になってくる
この映画は巷にあふれているような自分に投影させる映画でもあるけれど、
それと同時に客観的に観させることで理解が深まるようにできている
この客観的に鑑賞するというのが見逃しがちなポイントになってくる
映画は老手品師が時代の波に取り残されて、どんどん落ち目になっていくところから始まる
そうすでに映画がはじまった段階でこの老手品師という主人公は終わりに向かっているんだ
この映画はほとんどセリフがない
観客はパントマイムのような映画を観ながら物語を体験していく
おそらく脚本を描いたジャックタチという人がパントマイムが得意な役者だったということも関係していると思う
パントマイムでは嘘は表現できないと言ったのはたしかチャップリンだったと思うが、
このイリュージョニスト自体がつかみどころのない幻想という上に成り立っている
主人公は手品師なわけで、劇中でも観客に手品を見せて(幻想)を与えている
でも時代の波に取り残されて(1950年代が舞台なので)電気やテレビやロックやカンカン踊りのようなものに押されていく
ここでも一つ皮肉なのは、手品はもっともわかりやすい「幻想」なんだけど、テレビやロックやほかの娯楽も所詮は幻想なんだってこと
劇中では主人公の手品はさっぱりウケないが、奇抜なロックグループは大ウケしている
もちろんロックグループのほうが若くてイケメンでというのもあるだろうが、しょせんは彼らも舞台の上では演じているのであって、
舞台を観に来ている観客も幻想を観ているにすぎない
それなのに手品のほうは最初から幻想(タネも仕掛けもある)がわかりやすい芸であるためウケないのである
調子に乗って人の出番をつぶしてまで予定外のアンコールを連発したり、幕が下りたら女の子のような歩き方で階段を下りていくなど、
おおよそこのロックグループがそんなに魅力的とは思わないように映画は作られている
このわかりやすい幻想が受け入れられないというのはなにも手品に限ったことではなく、ピエロや腹話術師も出てくる
いずれもパッとせず、ピエロは自殺を考え、腹話術師は大事な人形を手放してしまう
ロックグル‐プの後でようやく出番がきた主人公の手品を観るのは母親に連れられた女の子のみ
でもその女の子すら、主人公の手品のタネや仕掛けを見破ってしまう
都会の女の子にタネを早々に見破られるというのが、あとに登場する田舎少女への伏線になっている
主人公はどんどん都会から田舎へと旅をしていく
ここの景色の移り変わりもきれいだし、スコットランドへ行くきっかけになったスカートをはいた酔っ払いのおっさんなど
いちおう飽きない構成にはなっている
最終的に流れ着いたスコットランドの酒場でようやく主人公の手品は受け入れられる
その町では電気もまだ定着していないので、明かりはランプ
それでも主人公の手品の上演のときだけは特別に電球をつけるなど、まだまだ時代に遅れているという描写がされる
物語の冒頭の劇場ではとても明るい電気のついた舞台だったのとはとても対照的である
主人公はその酒場の掃除をしていた少女になつかれる
これがいわゆる田舎少女として描かれている
この少女は主人公の手品を見てとても感動してくれたようで、主人公のことが気になる
主人公の部屋の前の廊下を掃除していたときに石鹸をすべらせてしまう
主人公は石鹸を拾い、手品を使って丸かった石鹸を四角い新品の石鹸にして少女に渡す
このことから少女は主人公を魔法使いだと思い込んだようで、世話を焼いてくれる
実は主人公はフランスを話し、少女はゲール語を話すのでお互いの意思疎通の会話はできないのだ
少女のみすぼらしい靴を見て、不憫に思った主人公は町で赤い靴を買って少女へ手品でプレゼントする
少女の目には魔法使いが魔法で出したように思ったのだろう、やはり感動する
赤い靴というのが実に気が利いている
赤い靴は昔から人目を惹く色であることから外交的(つまりは外の世界への関心)という意味になる
平たく言ってしまえば赤い靴=冒険ってこと
やはりこのあとの展開はおきまりのコース
主人公が田舎の町の興行を終えてフェリーに乗っていると、なんと少女もついてきてしまったのだ
当然切符をもっていない少女は主人公に切符を出してもらう
主人公はまたしても手品を使って切符を出す
フェリー港についてからもエジンバラまでついてきてしまう
当然旅費は主人公が出す
このあともエジンバラで共同生活が描かれるのだが、少女はおそらく初めての都会で見るものすべてが珍しいのか
主人公にコートや靴や高級レストランの食事などをねだる
この少女のオネダリに主人公が一生懸命に応えて、ものを買い与えるのが後半の主な話の流れとなる
少女は徐々にボロをまとった田舎少女から白いコートに白いハイヒールを履いて髪もセットした今風な都会少女へと変化していく
この映画のストーリーが酷評されるのはここだろう
少女のオネダリに応えるために老手品師の主人公が夜間バイトをしたりして必死に金を工面するシーンが延々と続き、
それと並行するようにピエロが自殺を図ったり、腹話術師が人形を手放してしまい、落ちぶれてホームレスになるなど暗い内容が続くからだ
さらに老手品師はデパートのウィンドウで女性物の下着なんかを手品で見せるという、本人は全然乗り気でないような仕事までするはめになる
最終的に少女は近くに住んでいた青年とデートを重ね、それを見た老手品師は「魔法使いはいない」という手紙とお金と花束を残して、一人去る
っていうのがだいたいのストーリー
やっぱり暗い気持ちになるからっていうのと、少女がワガママに見えて耐えきれないっていうのがストーリーが酷評されている原因でしょう
でもね、これ、実は狙ってやってるんだと思う
主人公の老手品師がなんでこんなに少女に優しくするのかっていうのが映画のラストでわかる
老手品師がいつも大事に持っていた一枚の写真に写っていたのは小さな女の子
おそらく自分の娘とこの少女を重ねていたんだなっていうのがわかる
この映画のあらすじ紹介を見ると、少女と自分の娘を重ねて‐っていうのがいきなりずばっと書かれているけど
ほんとは映画のラストでようやくわかる作りになっている
これが実は大事な部分だと思う
あらすじ紹介では早急に答え(娘と少女を重ねている)っていうのが提示されてしまっているから、逆にこの映画のストーリーを
わかりづらくしてしまっている
ぼくが思うに、この老手品師の娘はすでに亡くなっているんだと思うんですよ
なぜそう思うかと言うと、最後に主人公が娘の写真を見た後ちょっとため息をついて空を見上げるんですよね
そしてその空は雨が降っているんです
実はこの車窓の景色を見るっていうお芝居はこの映画の中で何回か出てきます
最初は主人公がスコットランドにたどり着くまでに何度か出てきますし、少女とエジンバラに行くまでにも出てきます
でも最後の娘の写真を見た後のお芝居だけはちょっと違う気がするんです
というのも、車窓から外を見る↓
さらに空を見上げる↓
列車の外から主人公の顔を写してそれがだんだんパン(遠ざかっていく)っていう演出なんです
つまり主人公の娘への想いが車窓から空、空からはるか天まで続いている(そしてその空は雨模様)
これ、主人公の娘が天国にいるってことだと思います
しかもその娘の写真がかなり小さい頃のため、田舎少女よりもだいぶ幼いです
ようするにこの主人公はある程度大きくなった娘の育児をした経験がないってことがここでわかります
この映画はいろいろな視点から鑑賞できるすばらしい映画ですが、まずはこの基本を押さえておくと簡単になります
主人公が夜バイトをしたりしてまで少女のワガママに付き合ったのは、ようするに親バカなんです
だれからも認められない手品を、魔法だと思って感動してくれることがうれしくて少女の幻想を守りたかったっていうのは
確かにあると思います
でもそれだけだと、「少女がワガママすぎる」っていう話になっちゃうんです
育児をしたことがないってことは「しつけ」をしたことがなく、「しつけ」の仕方もわからないんです
親なら子供にワガママを言われることって普通だと思います
そして親バカなら子供のワガママを多少無理してでもきいてあげちゃうんです
魔女の宅急便っていう映画でも荒井由実が「小さいころは神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた」
って歌ってますが、小さい子供のワガママをきいちゃうのは親バカならだれでも経験することだと思います
でも当人はわからないか、わかっていてもやめられないんですよね
だんだんワガママがエスカレートしてきたあたりでようやく「しつけ」っていう話になるんです
この親バカって周囲から見ると、なんでそこまでやるの?とか思うくらいのことだと思うんです
この映画は田舎少女のワガママを見て、観客が不快に思ったならそれで成功なんですよ
親バカっていうのは周囲から見るとこの田舎少女のワガママと一緒なんです
でも意外と見えないっていうかわからないんです
とくに主人公はわからない
どうすればいいのかわからないんです
田舎少女はゲール語しか話せなくて主人公とは意思疎通ができないっていうのも、幼い子供と親を表していると思います
なんとなく感情はわかっても難しいことまではコミュニケーション取れない感じ
幼い子供と親を田舎少女(都会を知らない幼い少女)と老手品師(歳をとり必死に幻想を見させる)っていう構造です
当然、親ですからいつかは子離れするわけで、映画でもちゃんと近所の青年というキャラクターが田舎少女とくっつきます
これも実に象徴的なシーンです
最後は雨が降る中、少女のコートを雨除けにしながら二人は夜の街に消えていきます
通りには傘を持った通行人が大勢いますが、それをかきわけるようにして進んでいきます
ワガママばかりで育った少女と、その無知につけこんだ青年の未来を暗示しているように思えます
この青年は昼間っから仕事もしないで本を読んでいるような奴で、デパートで田舎少女を見つけるやすり寄ってくるような男です
ネックレスを少女が小銭で買おうとして、当然買えずに少女は青年のほうを見ますが、青年は肩をすくめるだけ
この青年もべつにお金持ちってわけではないんです
そして雨が降ってきても少女のコートを雨除けにして(一応少女を小脇に抱えてはいますが)利用する男なんです
この青年と少女がキスをするショーウィンドウのマネキンがまるでアダムとイブのように配置されているのも象徴的で
このマネキンは全裸なんです
アダムとイブも知恵の実を食べてから局部を隠すようになりますが、全裸ということは知恵はないということ
この二人には知恵はないんですね
そしてそこで初めて二人はキスをする
そのあとで雨が降る通りを傘をさした通行人の流れに逆らうように進んでいくんです
通りにいる傘をさした通行人は、世間一般でいう大人(危険回避能力がある)を表していて、
それに逆らって進むっていうのはこれから人生の荒波にもまれるっていうの表しているような気がします
でもこの映画ではこれを肯定しているように思えるんです
というのは最後の主人公が町を離れる列車のシーン
真向いの席で小さな子が鉛筆を落としてしまいます
主人公は拾ってあげて、手品で子供に鉛筆を渡すんですが、このとき
主人公も鉛筆を持っていて、書いていたんですね
主人公の鉛筆は長く、子供は絵を書いたりでかなり使っているのか相当短くなってしまっています
今までの主人公だったら自分の使っている長い鉛筆を手品で出してあげて、驚かせてあげてたと思うんです
でも主人公が手品で出したのは、もともとその子が使っていた小さな鉛筆のほうでした
これ、すっごく大事なシーンです
親の子供への接し方の理想をここで描いているんだと思うんです
1を2にするのではなくて、0を1にすることなんじゃないかと
なにかに行き詰ったときに、もとの状態にしてあげることじゃないかな
ここでは鉛筆というわかりやすい例になっています
短い鉛筆(1)を失くし(0)、悲しむ子供に、長くなった鉛筆(1を2にする)ではなく
短い鉛筆を差し出すということ(0を1にする)
これが正解なんだってことですね
一番最初に田舎少女に手品をしたときも、丸い石鹸を新品にして渡すのではなく、丸い石鹸のまま渡すべきだったんです
まあ多少、渡すときに髪の中からとか口の中からとか驚きはあってもいいかもしれませんが、
もとの状態に戻してあげること、これが大事なんだと映画では言っている気がします
なにかに詰まった時にそれ以上の状態にしてしまうのはやりすぎであって過保護ってことなんでしょうね
ついついやりたくなってしまうのですが、過度な状態にしてしまうと子供はそれが当たり前になってしまう
子供はうれしくてもっともっととせがみ、それが親もうれしいから無理をしてしまい、ワガママが連鎖するという
親バカをとてもうまく表現できていると思います
このラストシーンの小さな女の子のほうが主人公の写真に写っている娘と年恰好は近いです
田舎少女よりも近いので、より娘の面影に重ねてしまうと思うんです
単なる親バカだったら相も変わらず長いほうの鉛筆をあげてたはずです
でも、主人公はもう親バカではないんです
そして田舎少女と過ごしたことで「正解」を見つけるんです
「正解」を見つけたことで、本来はできなかった娘のしつけ(育児)をできた気がして
長年の喪失感がようやく癒えたんでしょう
自分の人生を幻想でごまかさずに生きる決心がついたんだと思います
だからこそ主人公は手品に必要な道具やウサギを手放したんです
おそらく、娘の喪失に耐えられなくなり手品という幻想にこだわりつづけたんじゃないかなと思うんです
娘の喪失に向き合えて幻想ではなく(たとえ他人で、つかの間のことであっても)、娘と過ごし、娘の独立(男とくっつく)ところまで
経験できたことが主人公を立ち直らせて新しい人生へと進ませることになった気がします
一応、時代遅れになったピエロが最先端の象徴である電気のコードで首を吊ろうとしたり、その自殺を田舎少女の
シチューを食べて思いとどまるなんていうほっこりエピソードもあります
ほかにも主人公はショーウィンドウの仕事が嫌でやめてしまいますが、一応食べていくことはできたはずなんですね
我慢さえすれば
腹話術師も人形を手放してしまってホームレスになっちゃうんですが、質屋でも値段がどんどん下がって最終的には
フリーになっていましたから、街頭でもなんでもやろうと思えばできるはずなんですね
やっぱりそういうのができない、一種のプライドみたいなものがあるんだなっていうのが伝わってきました
主人公たちが苦しい立場に追い込まれているのは確かなんですけど、一応解決法というか答えというのが存在していて
本人たちは気づかなくても、それを見ている観客にはわかるようになっています
それがあえて、ドアップを使わないセリフを極力を排除することによって、観客を観察者にするスタイルと非常にマッチしているように思います
ただのもの悲しい映画っていうわけではなくて、だれしも経験しうること(人生の縮図)を温かい絵で描いた作品です
とてもすばらしいと思いました